環境計量士(騒音・振動関係)の試験は、専門2科目と共通2科目で構成されています。
今回は、専門科目の1つ「環境計量に関する基礎知識(物理)」(以下、環物)の勉強方法について、押さえるべきポイントを取り上げます。
なお、令和6年12月実施(第75回)で合格しています。
また、前提として私は理系(化学系)の大卒です。
経済産業省HPの「過去の計量士国家試験問題」に、過去5年分の過去問が掲載されています(2025年7月13日現在)。問題のレベルはこちらで確認してください。
私は、『環境計量士試験[騒音振動・共通]合格問題集』を利用しました。また、無料でアクセス可能な過去問も利用しました。
環物のレベルは、基本的には高校レベルの物理です。
最初の5問は、環境基本法1問、騒音規制法2問、振動規制法2問です。
まず、過去問を見ると、出題形式や出題されやすい箇所がわかると思います。これらの法令は量が多くないので、全文を読んでおけば対応できると思います。基本法は1問しか出ないので、深追いする必要はなさそうです。
この5問は、できる限り取りたいところです。
残りの20問は、分野別にどのような問題が出るかを分析する必要があります。
力学5問、波動3問、光3問、熱3問、電磁気4問、原子2問、で出題される可能性が高いはずです。
問題ごとにレベルの差があるため、過去問をベースに勉強して、各分野で基礎レベルを身につければ、6割を取ることはできるでしょう。
試験時間が80分なので焦る必要はないと思いますが、解法が思いつかない問題は捨てた方がいいと思います。
単純な式を選択する問題や単純な計算問題も割とあるので、単位や次元に注意して、そういった問題を落とさない方が重要です。

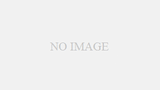
コメント