一般計量士の試験は、専門2科目と共通2科目で構成されています。
今回は、専門科目の1つ「計量に関する基礎知識」(以下、一基)の勉強方法について、押さえるべきポイントを取り上げます。
なお、令和4年12月実施(第73回)で合格しています。
また、前提として私は理系(化学系)の大卒です。
経済産業省HPの「過去の計量士国家試験問題」に、過去5年分の過去問が掲載されています(2025年10月12日現在)。問題のレベルはこちらで確認してください。
私は、『一般計量士国家試験問題 解答と解説 一基・計質 第68回~第70回』を利用しました。また、無料でアクセス可能な過去問も利用しました。
一基のレベルは、基本的には高校レベルの数学と物理です。
前半12問は高校数学です。
分野はバラバラで幅広く出題されますが、問題のレベルは易しいものがほとんどです。
そのため、分野別の対策は特に必要がなく、過去問の演習で十分だと思います。
10/12を取れると余裕ができるでしょう。
後半の13問は高校物理です。
物理も幅広い分野から出題されます。私の感覚では、力学・原子・熱の出題が多く、波動・電磁気の出題はやや少なめです。
得意・不得意には個人差があるため、過去問を見て得点源にする分野を作っておくのがいいと思います。
私は数学の方が簡単だと感じたため、数学でリードを作って物理は半分でいいと考え、結果として数学10/12物理7/13で合計17/25でした。
得点しやすい分野は人によって違うと思いますが、一基も計質も点を取る難易度はあまり変わらないので、基本的には15点を少し上回る程度を目標にするのがよいと思います。

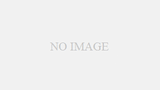
コメント