2021年12月に環境計量士(濃度関係)、2022年12月に一般計量士、2024年12月に環境計量士(騒音・振動関係)に合格しました。
試験については、経済産業省のHPを確認してください。
例年、6月に試験が公示され、7月に願書を提出することになります。
経済産業省HPの「過去の計量士国家試験問題」に過去5年分の過去問が掲載されています(2025年3月30日現在)。以前はもっと載っていたような気がしますが、掲載の方針は不明です。
環境計量士(濃度関係)
前提として、私は理系(化学系)の大卒です。
また、この試験を受験する前の2021年10月に水質関係第1種公害防止管理者に合格しています。
濃度関係は2021年12月に受験しました。勉強期間は約1か月でした。
『環境計量士試験〈濃度・共通〉攻略問題集 2020年版』を利用しました。
この本に掲載されている7年分の過去問をひたすら解きました。分野別のレベル感と出題傾向は過去問を見ればわかると思います。
目標点は15、15、13、18に設定しました。
試験の結果は、環化17/25、環濃15/25、法規14/25、管理19/25で合格でした。
環化は高校レベルがベースですが、一部の問題は大学教養レベルだと思います。
環濃は基本的に過去問を覚えられれば対応可能だと感じました。
法規は6割に到達しなかったのですが、管理で補いました。法規は出題傾向がイマイチ掴めませんでしたが、管理は傾向がわかりやすく、点数が安定しやすかったです。
一般計量士
一般計量士は2022年12月に受験しました。勉強期間は約2週間でした。
『一般計量士国家試験問題解答と解説 一基・計質〈計量に関する基礎知識/計量器概論及び質量の計量〉 第68回~第70回』を利用しました。さらに、この本に掲載されていない過去問を5年分利用しました。
濃度関係を合格しているため、共通科目は免除です。
過去問を見ると、一基の25問中12問が数学で、解きやすい問題が多い印象を受けました。計質も計算問題が単純なものが多い印象で、これを落とさなければ大丈夫かなと思いました。
目標点は17、15に設定しました。
試験の結果は、一基17/25、計質15/25で合格でした。
一基は数学で10/12取れたので狙い通りでした。
計質も計算問題の出題が多めで助かりました。
共通科目が免除だったおかげかもしれませんが、計量士の中で一番簡単だった印象です。
環境計量士(騒音・振動関係)
騒音・振動関係は2023年12月に受験しました。勉強期間は約2週間でした。
『環境計量士試験[騒音振動・共通]合格問題集』を利用しました。
この本に掲載されている7年分の過去問をひたすら解きました。環物は理解できない問題が多かったのですが、時間がなかったので諦めました。環音は計算問題を取れれば6割は取れるかなという印象でした。
目標点は15、15に設定しました。
試験の結果は、環物13/25、環音15/25で不合格でした。合格点は29点でした。
環物を見直してわかったのですが、2問ほど単純な計算ミスをしていました。試験時間の80分で解き終わらなかったのですが、解答の方針が思いつかない問題は捨てて、見直しに時間を費やすべきだったのかもしれません。とはいえ、全体的に高校レベルの物理の理解が足りていないことが主因でした。
環音は典型的な計算問題は落とさなかったため15点は取れたのですが、基本的な内容を理解していないため、過去問と出題形式が変わると解けないことがわかりました。
2回目は2024年12月に受験しました。勉強期間は2週間でした。
前年同様、『環境計量士試験[騒音振動・共通]合格問題集』を利用しました。
前年の記憶があったので勉強は楽でした。前年の反省を活かして、環物は出てくる式の理解に努めました。環音は計算問題を落とさないことと、理論部分の理解に努めました。
目標点は17,17に設定しました。
試験の結果は、環物17/25、環音19/25で合格でした。
環物はわからない問題が多くて焦りましたが、環音はかなり簡単でした。
科目ごとの勉強法や攻略法については他の記事で書きたいと思います。

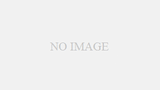
コメント